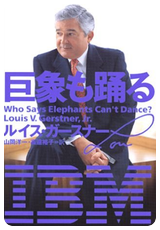「★ IBMという巨象をいかにして、再生したか?」
この本を読むきっかけは、私が今、自分の会社のホームページを作るのに使っている、QHMというソフトを開発した「北摂情報学研究所」という会社の亀田社長からのメルマガです。
メルマガの内容は
今の時代は同じ会社、同じ職業で一生を過ごせる人は、ほとんどいないでしょう。
現代は技術革新とグローバル化でいずれ、
・職業を変えるか
・会社を変えるか
という選択を迫られます。
その例として、あの「IBM」でさえ時代の変革の波に洗われて、会社存亡の危機に直面した時期があったことをあげています。
以下、亀田社長のブログの抜粋。
=============================
世界的な企業も、変わり続けている
=============================
もう20年以上前ですが、「巨像も踊る」という本が有名になりました。
巨像とは、IBM(世界屈指のコンピュータメーカーだった)です。
IBMは、メインフレーム事業(パソコンの前の世代のコンピュータ)から見事に、PC事業に転身しました。
しかし、今度は、そのPC事業をすべて売却し、
システム開発や、提供をメインとする「ソフトウェア」の会社になりました。
しかし、それでも、まだ変化が必要で、
「ビジネスコンサルタント」
という立場に変わりつつあります。
=========================================
と言うことで、ちょっと古い本ではありますが、「巨象も踊る」をアマゾンの中古本で、500円(送料込)で買って読みました。(^^;)
(亀田氏は20年以上前と書いていますが、2002年12月初版なので12年前ですね。)
その要約と感想を書いてみたいと思います。
この本の内容は一言でいうと、
1960年代から1980年代にかけて、大型のメーンフレームコンピュータで成功し、世界中で30万人の社員を抱えるまでになった「IBM」が1980年代後半に入って、ワークステーションによる「オープンシステム」の時代を迎へ、今までの「メーンフレーム」中心のビジネスモデルが足かせとなり、大赤字に直面します。
巨象も遂に倒れるかと思った、その時に「ルイス・ガースナー」が外部からIBMの会長兼CEOとしてやってきて、IBMを再び輝く会社に蘇らせます。
この本はガースナー自身が、「いかにしてIBMを蘇らせたか?」について書いた本です。
最初にガースナーの生い立ちと経歴が書いてあります。
〔経 歴〕
1942年、ニューヨーク生まれ。大学卒業後、ハーバード大学のMBA取得。最初に「マッキンゼー」に入社し、約12年間経営コンサルティングを経験。
その後、「アメリカン・エキスプレス」の旅行関連サービスグループの責任者として、アメリカン・エクスプレスカードなどの事業の責任者を約11年間担当。
そして、ビスケットの「ナビスコ」とタバコ産業の「R・J・レイノルズ・タバコ」が合併した「RJR・ナビスコ」のCEOとして、4年間経営に当たった。
その経験を買われ、1993年に「IBM」再建のためにスカウトされる。
〔CEO就任当時のIBMの問題点〕
① 製品市場の問題
・当時、市場はワークステーション(サンマイクロやヒューレットパッカードのUNIXシステム)などのオープンシステム、さらにはパソコンでのクライアントサーバーシステムへ急激にシフトしていた。
・そのため、IBMが得意なクローズされ、且つ高額な「メーンフレームシステム」は急激に市場シェアを奪われ、売上が落ちていった。
② 組織の問題
・地域、国ごとの独立王国状態で強烈な縄張り意識。
その結果、間接部門の人数が極端に多く、システムの重複、複数の予算などの問題が存在。
・「経営委員会(MC)」で重要事項を決定。
権限と責任が分散していた。重要案件も事前の根回しで決まり、経営会議は事後承認しているだけで形骸化していた。
・行き過ぎた「個人の尊重」。
「同意拒否制度」により、会議で決めた重要な事項も個人、或いは部門レベルで「ノー」と言って、実行を拒否できる信じられない制度があった。
③ 企業文化の問題
・外部の顧客の視点より、社内政治と縄張り争いの内向きな論理。
・1969年に反トラスト法(日本の独禁法のようなもの?)で提訴された。
その時に「市場シェア」「競争」「支配」「勝つ」などの言葉を使うことを禁止され、ライバルに対する闘争心が失われていった。
・家父長的な温情主義の社風で、年功序列的な給与体系と終身雇用。手厚い福利厚生。(高コスト体質)
・社内の手続き重視で服装規定から上司用のガムの買い置きの仕方まで、こと細かに文書で規定している。
〔ガースナーが就任直後に打った手〕
① 会社の分社化を阻止。
・市場のオープンシステム化に対応して、IBMをいくつかの子会社に分社化にする動きがあった。ガースナーは顧客に一体のソリューションを提供することこそIBMの価値と考え、一体経営を決断。
② メーンフレームの値下げを決断。
・利益の減額をカバーするために、独立王国の組織を本社が一体管理することで、間接経費の大幅なコストカットを同時に推進。
③「経営委員会(MC)」の廃止と「本社執行委員会(CEC)の創設。
④ 不要な資産(不動産や美術品、社有機など)の売却により、当面のキャッシュを確保。
⑤ 事業の再編(エンジニアリング)。
・例えば世界に128人いた最高情報責任者(CIO)を1人にする。266本あったの経理システムの1本化。155ヶ所のデータセンターを16ヶ所に減らす。31本あった社内通信ネットワークの1本化などのリエンジニアリングに着手。(数年掛けて、経費の大幅削減。)
〔ガースナーの経営哲学〕
① 基本哲学は「事業の絞り込み、スピード、顧客、チームワーク。」
② 市場と現場を重視。(我々のやるべきことを決めるのは市場である。)
③ 個人や部門中心でなく、チームワークで会社の利益を優先する。
④ 社内の組織や手続き重視から、原則重視。
(会議は問題解決に必要な人を地位や肩書に関係なく集める。)
〔IBMの新しい戦略〕
①「総合的なソリューションを提供する【総合サービス・プロバイダ】」を今後の戦略の基本とする。
(自社の製品にこだわらず、顧客に最適なシステムを提供する。)
② 地域ごとの独立王国を解体し、全世界的に、産業別12のグループに再編。
③ ブランド戦略の統一。
(社内各地で70社の広告代理店と契約し、部門が勝手に打っていた広告を本社で1本化し、広告代理店も世界で1社と契約した。)
④ 家族主義の手厚い福利厚生の見直しと、固定的な報酬制度の業績給への変更。(チームとしての全社の業績を重視)
以上、概要をかい摘んで書きましたが、要はガースナーの強力なリーダーシップと優れた戦略により、「IBM」は見事にコンピュータ業界のリーダーに復活しました。
ガースナーは単に強力なリーダーシップを持ち合わせているだけでは無く、ハーバードのMBAやマッキンゼーで訓練を受けた企業分析のスキル、特に経営上のデータを集めて読み解く力が多いに役立ったのもと推測されます。
そして、この物語の教訓は
① IBMのような世界中から秀才を集めたような頭脳集団でも、栄枯盛衰のサイクルからのがれられないこと。
② 外部から隔離された純血主義の組織は時間と共に世間の常識から外れた社風がはびこるが、中にいる人間には気がつかない。
③ セクショナリズムが横行し、内部紛争に明け暮れ顧客視点が失われて衰退の道をたどる。
などです。
このような状況に陥ると内部からの自己改革は難しく、外部からの強力な力で変革しないと変われなくなるようです。
(限られたプロしかなし遂げられない仕事で、誰にでも出来る仕事ではないですが・・・。)
((これは明治維新以来、外圧でしか変われない、日本の国家そのものにも通じるものを感じます。)
そして、ガースナーがこの本で一貫して強調しているのは、「顧客第一主義」の視点です。
ガースナーは度々、「我々のやるべきことの全てを決めるのは市場である。」とか、「市場こそが、すべての行動の背景にある原動力である。」、「顧客本位(顧客の立場で考える)」などと述べています。
組織の大小を問わず、過去に大きく成功したり、創業から時間経ち経営者が代わったりした場合に特に「顧客視点」が忘れられがちです。
最後にガースナーが成功の条件として挙げているのが、「顔が見えるリーダーシップ」であり、それの意味するところは「ビジネスへの情熱」「勝利への情熱」です。
成功した偉大な企業の経営幹部は、「全員が情熱を持ち、情熱を示し、情熱に生き、情熱を愛している。」と述べています。
我々も、このガースナーの教訓に学びなだら、日々の営業活動に励みたいと思います。
以上
【追伸】
本の最後の方に「付録」として、ガースナーが全社員宛てに送ったメールの例がいくつか載っています。その中から多くの会社にとって教訓になると思われる部分を抜粋してみました。
「以前にも当社には傑出した事業戦略があった。それらを全て読んでみた。驚くほど時代の先を読んだ戦略であった。
問題は戦略を実行して来なかった点にある。
会議に出席し、うなずいて賛成の意志を表明し、会議が終われば、それまで通りの仕事に戻る。
我々は変わらねばならないことで合意したが、変わらなかったのだ。
新しい戦略が必要だと話し、新しい戦略を作ったが、実行して来なかった。
業界を主導する地位を維持すると語ったが、維持するに必要な行動をとらなかった。」
また、彼は長年、オフィスに下記の標語を掲げていたそうです。
世の中には四種類の人間がいる。
・動きを起こす人
・動きに巻き込まれた人
・動きを見守る人
・動きが起こったことすら知らない人
(おわり)